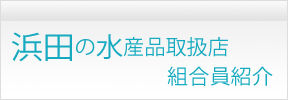1
1.カレイとヒラメ、よく似ている魚です。 この2つの見分け方は目の位置です。簡単に見分ける覚え方があります。
『○ヒラメに○カレイ』それぞれ○に入ることばは何?
Q1.A.左ヒラメに右カレイ(ただしマヌガレイだけは目が左側にあります)
 2
2.フグはいつ頃から食べられていたのでしょう?
①縄文時代 ②江戸時代
Q2.A.①縄文時代の多くの貝塚からフグの骨が発見されています。
島根県でも美保関町や松江市西川津の縄文時代の遺跡から骨が出土しています。
 3
3.マトウダイは口を前方に伸ばすことができ、エサを獲るのに役立ちます。
さて、どのようにエサを食べるのでしょう?
①伸ばした口で岩に生えている海藻をかじる
②小魚などを一瞬で吸い込む
Q3.A.②大きくあけた口で吸い込んで丸のみします。
 4
4.タイについてです。「魚の王様」と呼ばれるタイ。
では名前の由来は?
①ひらたい ②かたい ③めでたい
Q4.A.①その体形から平たい魚でタイと呼ばれるようになりました。
 5
5.トビウオは飛ぶことのできる魚ですが、およそどれくらいの距離を飛ぶことができるのでしょう?
①15m ②50m ③300m
Q5.A.②トビウオが飛ぶのはシイラなどの天敵から逃げるためだと考えられます。
 6
6.メダイについてです。九州南方で生まれたメダイは成長しながら日本海を北上してきます。
さて、その際に何暖流に乗って北上するのでしょう?
Q6.A.対馬暖流 対馬暖流に乗った旅は北海道まで行き、反転して生まれ故郷へ戻っていきます。
 7
7.サザエについてです。「猫にサザエ」ということわざがあります。
このことわざの意味はつぎのどちらでしょう?
①ものの価値がわからないこと
②大好きなものだが手の出しようがないこと。
Q7.A.②いくら好きなものでも猫の手ではサザエは食べられないこと。
 8
8.イカやタコは切っても血が出ない。
なぜ? もともと体に血がない。○か×か?
Q8.A.×:イカやタコの血は薄い空色をしているので、切っても見えないだけです。
 9
9.浜田ではノドグロ(アカムツ)が1年中水揚げされていますが、 ブランド化されている「どんちっちのどぐろ」は、何月から何月に獲れたものをいうのでしょう?
Q9.A.8月~翌年1月
この期間に漁獲され、かつ一定のサイズを超えるものに目印であるどんちっちシールを貼ります。
 10
10.アナゴについてです。マアナゴの卵は自然界で発見されている。○か×か?
Q10.A.×:マアナゴの生態はウナギと同様にわからないことが多く、自然界で卵が採集されたという報告はありません。
また、卵を持ったアナゴも自然界では発見されていないことから産卵場がどこにあるのかもわかっていません。